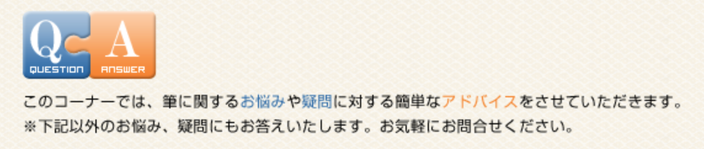

1.筆のおろし方は?

【太筆】
太筆は基本的には全ておろして使います。
筆の毛の弾力をうまく使っていただくと、筆本来の持ち味を出すことができます。
ただ、筆を使うことにあまり慣れていない方には全部おろしてしまうと線がしっかり書けなかったりするため、短峰(毛先の短い筆)気味の筆や、筆をおろす際に2/3くらいにして使うと良いです。
1.購入後、水にすぐにつけず、少しずつ回しながら先端から指で押しまわすようにほぐしていきます。
2.全てほぐれたら水につけて糊を落とします。このとき、根元から絞り出すようにします。
3.糊がとれたら、水気を絞り出し、形を整えて毛を下にして乾かします。
【細筆】
細筆は全ておろさず、1/3〜半分位をおろして使います。
1.購入後、指で1/3程度ほぐします。
2.ほぐれたところを少し水をつけて糊を取ります。

2.筆の洗い方は?

【太筆】
使い終わった筆は、必ず水で墨を落とします。
水道の水を筆洗(おわんなどでもOKです)にため、筆を優しくもみ洗いするように洗います。
綺麗な水で2〜3回すすいだら、指で根元から押し出すように墨を絞ります。墨が出てこなくなるまで繰り返してください。根元に墨が残ったままだと、根元に墨が溜まっていき使えなくなります。
すすいだら水気を絞り出し、形を整えて毛を下にして乾かします。
購入時についていたキャップは使わないようにしてください。キャップをすると乾燥しなくなり、湿気によりカビが生えやすくなったり根元から腐って毛が抜けることがあるからです。
【細筆】
使い終わった細筆は、墨のついている部分を水につけ、半紙で拭き取ります。その後、ぬれたティッシュや布巾でそっと墨を取り除きます。形を整えたら、太筆と同じように吊るして乾燥させます。
太筆も細筆も毛が乾燥したら筆巻きなどに入れて保管します。

3.長持ちさせるコツは?

筆を長持ちさせるには、使い終わったらしっかり洗うことです。
筆が使えなくなる要素は、割れる、墨が残る、毛が抜ける、毛が縺(もつ)れることです。ほとんどの場合は筆の洗い方に問題がありますので、しっかり洗うことさえ守れば長く使うことが出来ます。

4.筆が割れました、どうしてですか?

筆が割れる原因として以下のことがあげられます。
1.墨が根元に残っている
2.毛が抜けてしまった
3.毛が縺(もつ)れている
4.無理な扱い方をして、根元から割れをつくってしまう
それぞれの原因をなくすことが解決策になりますが、基本的には使い終わったらよく洗ってください。
※墨が根元に残ってしまった場合は、水につけながら押し出すように墨を揉みだしてみてください。
※水道の蛇口から出る強い水圧で洗うと筆が割れるもとになる可能性がありますのでやめてください。
※毛が抜けてしまった場合は、洗った後の乾燥が仕切れていなかった、もしくはキャップをつけたまま蒸らしてしまったために根元が腐ってきたためです。
※毛が縺れている場合は水につけたまま金櫛を通してほぐしていきます。
いずれにしても、毛が割れてしまった場合は筆を新しくされることをオススメします。

5.筆はどのような方法で選べばいいですか?

人により好みがあるとは思いますが、一般的には硬い筆から柔らかい筆にシフトしていくようです。また、毛の短い筆のほうが思ったように毛が動くので使いやすいのではないでしょうか。
伽藍では高校生以上の初めての方には使いやすい「観音」、中学生の場合には「花柳」、小学生の場合には「学友」をオススメします。
また、楷書から行書、草書へと行く場合は、「天楽」「二貂八羊」を、かな条幅には「長栄」「錦秋」、少し固めをお好みなら「朱雀」「大あけぼの」をオススメします。

6.その他筆について、注意することはありますか?

筆を使う際には硯の墨堂の部分(墨を磨るところ)ではあまり強く擦ることはなるべく避けてください。
硯は墨をするための道具、いわばヤスリのようなものであり、毛を炒める原因になります。
筆は購入直後から少しずつ書き手にあった変化をしていきます。
筆の毛に墨が入り込むことにより、こしが強くなってきたり墨の含みがさらに良くなったりしていきます。
上述したように、筆は少しずつ書き手にあった変化をしてきます。「なれ」という言い方もあると思いますが、ほで本来の性能を活かすことができるのは、変化した、成長した筆です。
筆を成長させるのも、楽しみの一つではないでしょうか?
